【iDeCo】2022年の法改正でより身近になる理由
昨今、お客様と面談していると「NISA、つみたてNISAと併せてiDeCo(個人型確定拠出年金)をやってみたい」というお客様が増えた印象を受けます。2021年11月現在で224万人以上がiDeCoに加入しており、今も増え続けています。そして今年の2022年にiDeCoが改正されることになります。
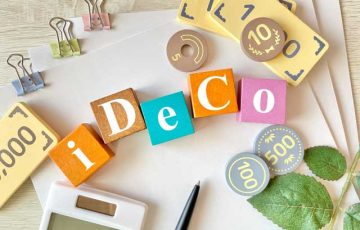 公的年金
公的年金
昨今、お客様と面談していると「NISA、つみたてNISAと併せてiDeCo(個人型確定拠出年金)をやってみたい」というお客様が増えた印象を受けます。2021年11月現在で224万人以上がiDeCoに加入しており、今も増え続けています。そして今年の2022年にiDeCoが改正されることになります。
 住宅ローン控除
住宅ローン控除
従来の住宅ローン控除では控除期間は最長10年間でしたが、消費税10%への引き上げにより消費税10%が適用されるマイホームを取得等した場合、控除期間が10年間から13年間に延長されました。
 相続対策
相続対策
遺言書は大きく2つの方法があり、公正証書遺言と自筆証書遺言に分けられ、自分で書いて完成させられる手軽さから、「自筆証書遺言」を選ばれる方が多くいらっしゃいます。しかし、その自筆証書遺言を使って、「相続人が財産分けを進めようと思ったのに手続きが進められない」という事例が見受けられます。
 戸籍
戸籍
日常生活を送っていると、知り合った人の名前の漢字に馴染みがなく、何と読めばわからないことがあります。
そのような場合、相手に何と読むか確認をした経験があるでしょう。
特に最近はいわゆる「キラキラネーム」といわれる名前の漢字からは読み方がわからず、「どう読めばいいのか」となることもあります。
しかし、今後そのような「キラキラネーム」を子どもに付けられなくなるかもしれません。
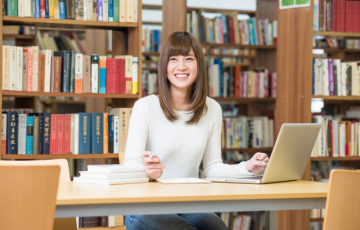 ライフプラン
ライフプラン
日本学生支援機構の「平成30年度学生生活調査」によると、大学生の47.5%が何らかの奨学金を利用しているという結果が出ています。
お客様と面談していますと「あと数十年、奨学金の返済が残っている」という方が多く見受けられます。
毎月返済できる方は良いのですが、非正規雇用の方や就職先の会社に馴染めず、仕事を辞めてしまい収入が安定しない方等、返済に困っている方がニュース等で取り上げられています。
出来るだけ子供に奨学金を使わせないために、どのような対策が取れるのかをお伝えしていきます。
 退職金
退職金
オーナー経営者は、会社員とは異なり定年はありません。しかし、いつかは引退してこれまで蓄えてきた資産や年金で生活を送ることになります。経営者の周りには、税理士や生命保険会社の人など金融商品に詳しい人がたくさんいると思いますが、意外にも、老後資金を計画的に積み立てていない中小企業経営者が多いことに驚きます。
そこで、中小企業経営者の老後生活のための主な退職金積立制度と公的年金の上乗せ制度についてご紹介します。
 お役立ち情報
お役立ち情報
日照権とは自分の建物に対する日照の利益を保護する権利です。ただし、日照権そのものを定めた法律はなく、他の法令や判例上、日照権が保護されています。とはいえ、社会共同生活を送っている以上、どのような場合であっても自分が満足いく日照の利益を受けられるわけではありません。では、どのような基準で日照権は保護されているのでしょうか。
 税制改正
税制改正
毎年のように環境に配慮した車が発売されていますが、これらの車を購入すると「エコカー減税」といわれる自動車重量税が減税される制度が適用されます。
今回は2021年度の税制改正によって改正されたエコカー減税や、2019年10月から導入された環境性能割について紹介したいと思います。
 家計の見直し
家計の見直し
現在、生命保険や医療保険に加入してる方は非常に多いと思いますが、もし、新型コロナウイルス感染症に感染してしまった場合、現在加入している保険でどの程度保障されるのか、不安を感じている方もいらっしゃることと思います。この機会にご自身で加入されている生命保険や、医療保険等の保障内容、保険会社の対応内容などを確認することをお勧めいたします。
 商標権
商標権
近頃の急速なオンライン化でネットショッピングの需要が増える中、実際に店舗に来店した顧客に向けて、内装デザインなどを工夫し、オンラインでは実感できない特別な体験を提供することが重要となってきました。外装デザインの観点からも、デジタル技術を駆使した「プロジェクションマッピング」の画像などを保護する必要性も高まってきました。
 ライフプラン
ライフプラン
コロナウイルスの影響で私たちの生活様式は大きく変わりました。それに併せ、家計の管理方法も変えていかなければなりません。今までよりも家庭での時間が増えたと思いますので、この機会に大きく家計の管理方法を見直してみましょう。
 ライフプラン
ライフプラン
2020年は新型コロナウイルスの影響で家計の収支が変わり、家計管理が難しい年だったのではないでしょうか。年も変わりましたが、今後もコロナウイルスと共存しながらの生活はしばらく続きそうです。今までと同じようなことをしていても変わりませんので、今年から心機一転、家計の見直しをしてみてはいかがでしょうか。