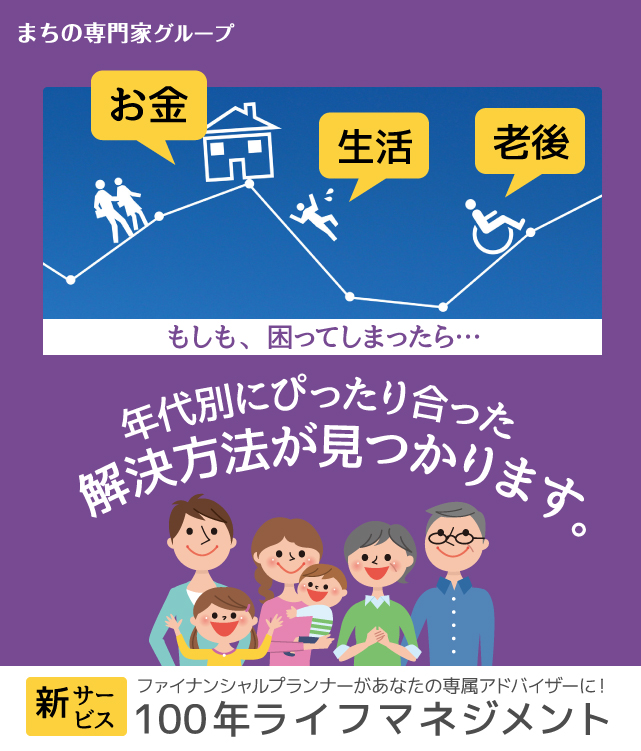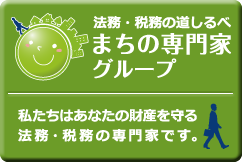昨今、コロナ禍ということも相俟って、未成年者、特に小学生でもスマートフォンを持つことが増えました。
それにより、お互いに自宅にいて通信で遊んだり、また、自宅で一人でゲームなどをして遊ぶことも増えています。
同じく、ゲーム機を使用したオンラインゲームをする子も増えているようです。
もっとも、これらを使用してゲームをする際に、親に黙って課金をしてしまうケースも増えているようです。
親からしたら、知らないうちに多額の請求が来てしまい、とても驚くことでしょう。

このような事態に対応するための事前の対策としては以下のことが考えられます。
① オンラインゲームで課金する場合のルールを家族で話し合いましょう
② 保護者のアカウントで子どもに利用させず、保護者のアカウントで子どものアカウントを管理、保護できるように「ペアレンタルコントロール」を利用しましょう
③ スマートフォン端末では保護者のアカウントで子どもに利用させる場合、保護者が子どもの「課金を防ぐ」「課金に気づく」ために、事前に保護者のアカウントの設定を確認しましょう(出典:国民生活センターホームページ)。
すでに子どもが課金していた場合
未成年者は「制限行為能力者」と言い、一部の場合を除いて法律行為を行なうことはできません。
特に親(正確には親権者や未成年後見人)の同意なくして、契約などの法律行為をすることはできません。
親の同意なくしてなされた契約行為は、遡って取消すことができます。
これを「未成年者取消権」と言います(民法第5条)。
したがって、子どもが親の同意なく課金した場合、事業者に対して未成年者取消権を行使すれば、「課金する」という契約は取り消されます。
もっとも多くの場合、課金すれば登録してあるクレジットカード会社が事業者に支払いをすることになりますが、子どもが勝手に課金したような場合にはクレジットカード会社は事業者にお金を支払うという規定になっていることが多いです。
そうすると、親としては事業者に対して直接課金した金額を返金するよう、交渉することになるでしょう。

未成年者が「詐術」を用いた場合
また、子どもが課金する際に自らの年齢を偽って「成人である」と虚偽の情報を入力することもあり得ます。
このように、未成年者が「詐術」を用いた場合、取消権を行使できなくなります(民法第21条)。
「詐術」とは、制限能力者であることを誤信させるために、相手方に対し積極的術策を用いた場合に限るものではなく、制限能力者が普通に人を欺くに足りる言動を用いて相手方の誤信を誘起し、または誤信を強めた場合をも含んでいると解されています(最高裁 昭和44年2月13日判決)。
ただし、当該最高裁判例も昭和44年のものであり、現代のスマートフォンなどの課金までも視野に入れたものとは言えないでしょう。
電子商取引等に関する準則
そこで、参考になるのが経済産業省の「電子商取引等に関する準則」です。
対面の取引ではなく、電子商取引であるという特色、また、事業者と未成年所の保護のバランスをとるため、「単に未成年者が成年である旨回答したことだけをもって判断されるものではなく、事業者が故意にかかる回答を誘導したのではないかなど、最終的には取引の内容、商品の性質や事業者の設定する画面構成等個別の事情を考慮して、判断されるものと解される」とされています。
取消すことができない可能性のある例として、「未成年者の場合は親権者の同意が必要である」旨警告した上で、年齢確認措置をとっている場合」です。
取消すことができる可能性のある例は、
「単に“成年ですか”との問いに“はい”のボタンをクリックさせる場合」
が挙げられています。

以上からすると、やはり子供には事前に課金させないようにすることが最も重要であることは間違いありません。
それでも課金された場合は、できるだけ早く未成年者取消権を行使するべきでしょう。
投稿者プロフィール

- 当事務所はさまざまな分野の法律紛争に対応しておりますが、案件としては相続事件がやや多めになっております。相続対策は早いほど効果的。気になることがある方は一度ご相談ください。平成25年4月 当事務所の弁護士たちで、東洋経済新報社より『新版 図解 戦略思考で考える「相続のしくみ」』を上梓しました。事務所は、アクセスの良い銀座一丁目駅にあります。まずはお問い合わせください。
最新の投稿
 トラブル・訴訟2025年4月24日【未成年者取消権】子どもが知らないうちにゲーム課金してたら?
トラブル・訴訟2025年4月24日【未成年者取消権】子どもが知らないうちにゲーム課金してたら? 特別寄与分2024年12月23日【特別寄与料】献身的な長男の妻に遺産を取得させる方法
特別寄与分2024年12月23日【特別寄与料】献身的な長男の妻に遺産を取得させる方法 カスタマーハラスメント2024年8月7日【カスハラ対策】クレームの範囲を超えた時にするべき対応
カスタマーハラスメント2024年8月7日【カスハラ対策】クレームの範囲を超えた時にするべき対応 トラブル・訴訟2024年4月25日【法令遵守】コンプライアンスに違反すると何が起こる?
トラブル・訴訟2024年4月25日【法令遵守】コンプライアンスに違反すると何が起こる?
100年ライフマネジメント
月々1000円(税込)で専属アドバイザーには何度でもご相談いただけます。